はじめに
前回の記事(第1部)では、「問題社員」の定義や早期対応の重要性、見極めポイントについて詳しく解説しました。本記事(第2部)では、その問題社員に対してどのように合法的かつ効果的に「退職勧奨」を行っていくか、その具体的ステップと実務上の注意点、さらには「退職勧奨代行サービス」を活用するメリットについて、社会保険労務士の視点から詳述します。
第1章:退職勧奨とは何か?退職強要との違い
-
-
-
退職勧奨は「任意退職の提案」にすぎず、強制ではない
-
退職強要(違法)と退職勧奨(合法)の明確な線引き
-
判例で見るアウト・セーフライン
-
実務上ありがちなNG発言・態度例
-
-
第2章:退職勧奨を行う前の準備ステップ
第3章:退職勧奨の具体的ステップ【面談の流れ】
● 「他の社員への悪影響」が最大のリスク
問題社員の存在が許容される職場では、真面目に働く社員のモチベーションが低下し、「頑張っても評価されない職場」という不信感を生みます。これにより以下のような二次的被害が発生します。
-
業務品質の低下
-
優秀人材の離職
-
職場の閉塞感・内紛の増加
Step1:事前通告(通知書の発行)
-
「ご相談したい件があります」程度でOK
-
通知書例(社労士監修テンプレート)
Step2:1回目面談
-
面談の目的は「気づきと自己選択」を促すこと
-
感情的対立を避ける話法(例:「将来的なご自身のキャリアを一緒に考えましょう」)
-
社労士・第三者の同席が効果的
Step3:2回目面談(本人意向の確認)
-
再確認と選択肢の提示
-
解雇回避努力を示す(他部署異動案、教育機会提示など)
Step4:退職意思の確認と同意書の作成
-
退職届よりも「合意退職書面」の作成が望ましい
-
有給消化・退職金等の条件提示
第4章:退職勧奨後のトラブル防止策とリスクマネジメント
●
-
退職後の労基署通報・訴訟対策
-
「自主退職」であっても録音・記録は必須
-
ハラスメント被害者との関係整理
-
離職票の備考欄と社会保険手続き
第5章:退職勧奨代行サービスを活用するメリットと成功事例
1. 第三者による冷静な進行
-
社内の私情・人間関係を排除できる
-
感情的対立を避けてスムーズに合意へ
2. 法律リスクの最小化
-
弁護士・社労士による法的監修
-
記録・書面の整備サポート
3. 成功事例の紹介(匿名加工)
-
例1:業務命令違反を繰り返した従業員の円満退職
-
例2:勤怠が極端に悪い社員の対応
-
例3:セクハラ加害疑惑があった管理職の処遇
SEOキーワード:退職勧奨代行、退職勧奨 成功事例、退職勧奨 社労士、退職代行 違い
第6章:退職勧奨の失敗パターンと回避策
-
失敗例①:1回の面談で結論を急いだ
-
失敗例②:上司単独で行い、録音も記録もなし
-
失敗例③:「辞めた方がいい」といった強要発言
第7章:退職勧奨を成功に導くための10のポイント【保存版】
-
-
就業規則・評価制度の整備
-
問題行動の記録化
-
面談は複数回に分ける
-
合意書の書面化
-
話法・トーンに注意
-
感情的対立を避ける
-
第三者(社労士など)の同席
-
録音・議事録の作成
-
有給・退職金等の条件提示
-
トラブル発生時の相談先を確保
-
まとめ:企業にとって退職勧奨は経営リスクの最小化戦略
退職勧奨は「追い出し」でも「懲罰」でもなく、企業と社員の「関係整理」です。問題社員対応を先延ばしにするほど、社内の生産性は落ち、優秀な社員の離職リスクも高まります。合法かつ円滑な退職勧奨を行うためには、専門家の知見と第三者性を活用することが極めて効果的です。
「退職代行」の逆、「退職勧奨代行」こそ、今後ますますニーズが高まる人事戦略といえるでしょう。
付録:退職勧奨に関するよくある質問(FAQ)
-
退職勧奨は何回まで面談すればよい?
-
書面化は必須か?
-
退職金や有給をどう取り扱うか?
-
ハラスメントを起こした社員にも使える?
-
社内の相談窓口は誰にすべきか?
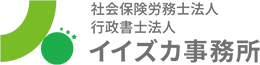




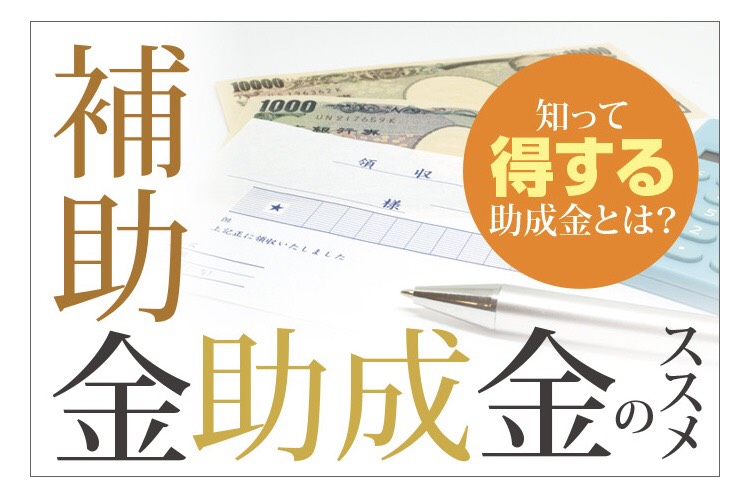
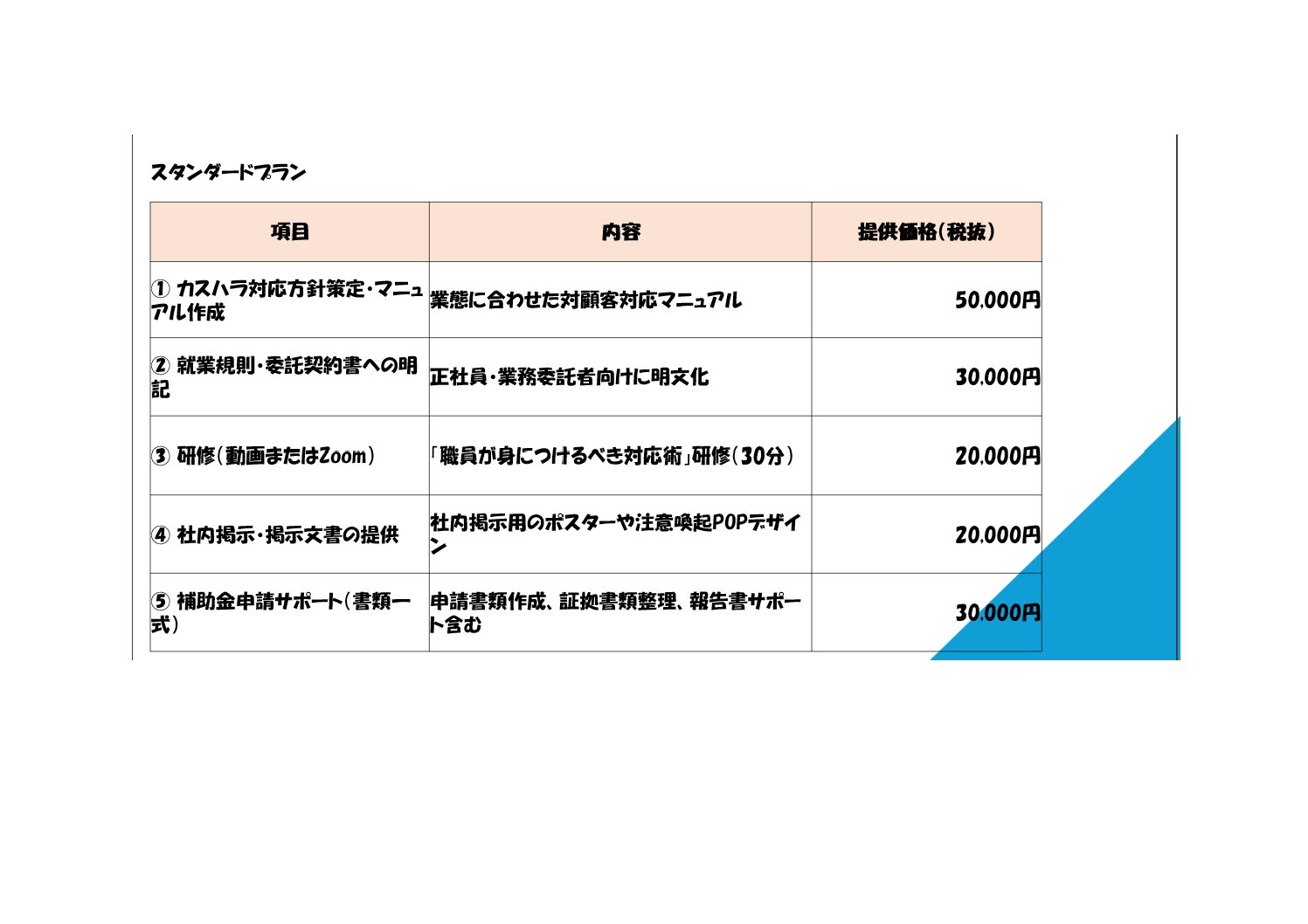
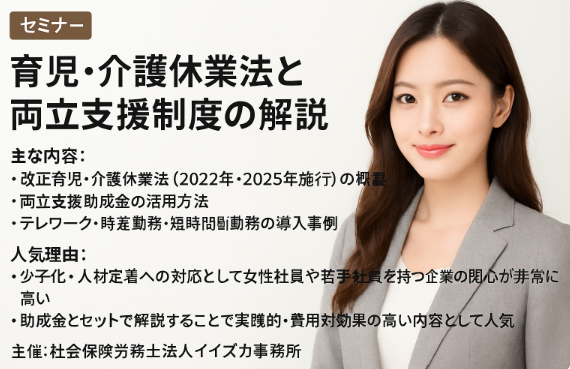
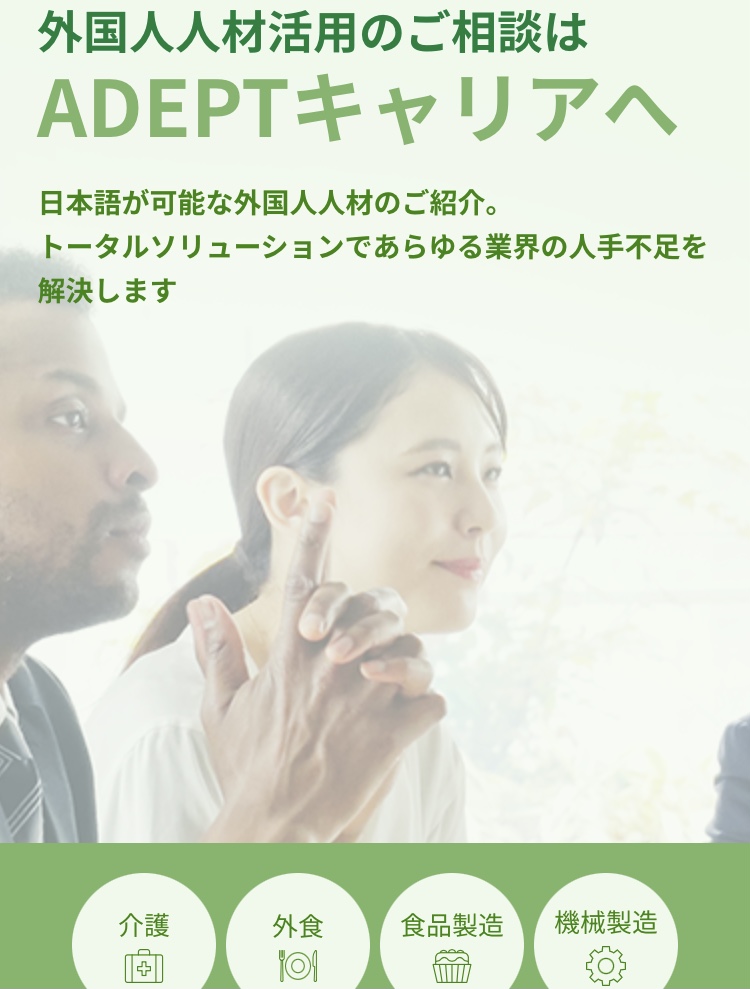


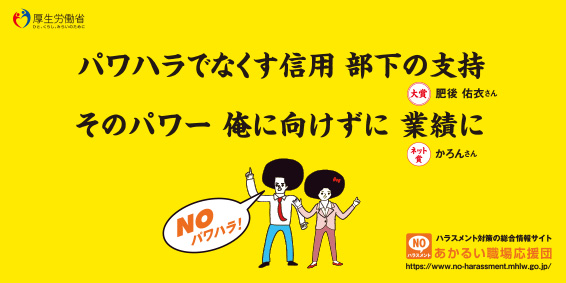
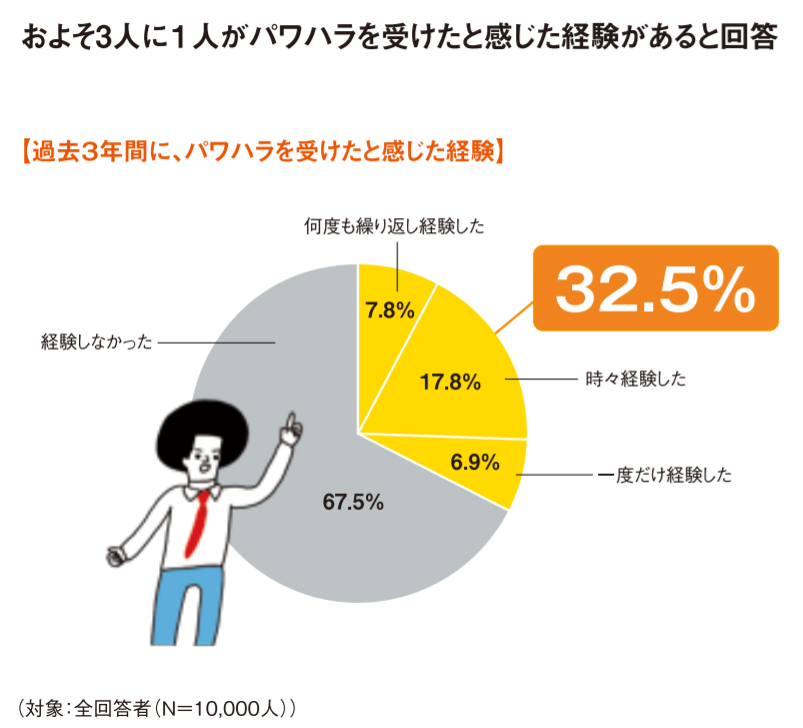
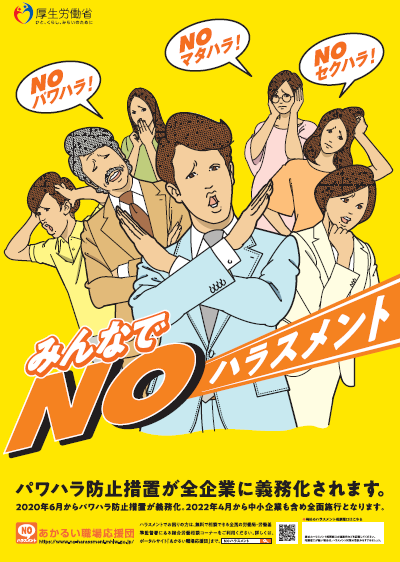


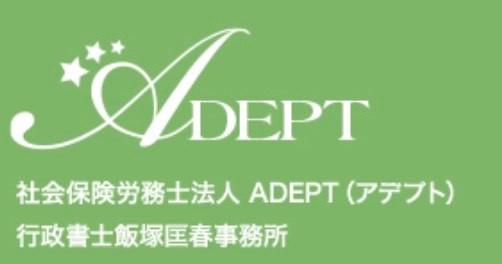

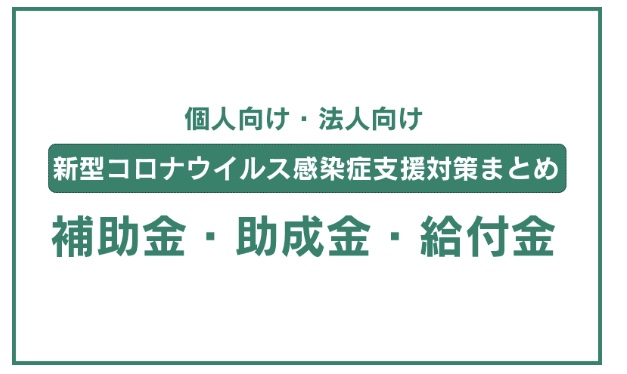







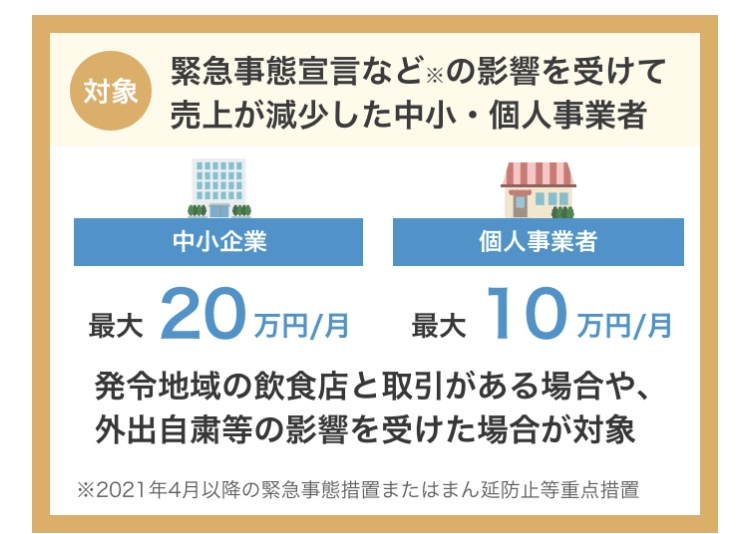


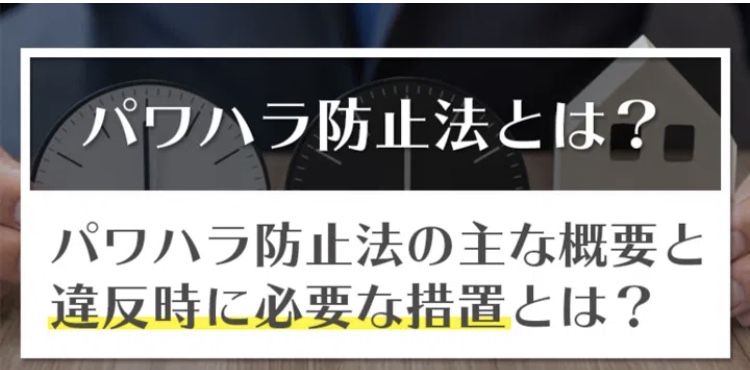
 前へ
前へ
